いい論文を書いている!を測るh-index
スポンサードリンク
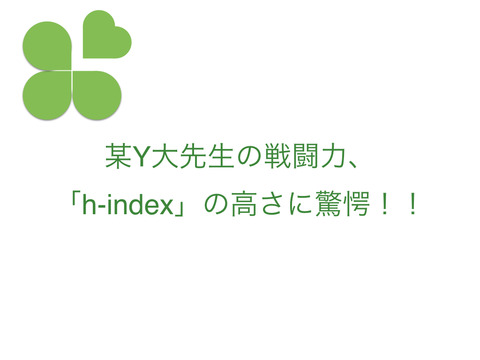
はじめに
わたしの臨床研究の出会いは、わたしが敬愛するブログ
整形外科医のための英語ペラペラ道場
がきっかけです。
臨床研究デザイン塾の事が記事にしてありました。
すぐにこの本を購入し、わたくしも勢いにまかせて参加いたしました。
わたしの臨床研究の学びの出会いは、
— とぜんな脊椎外科医@四つ葉スパインクリニック (@yotsuba_spine) August 23, 2019
整形外科@sugimovic@ysugimoto先生
が運営されていたブログがきっかけです。
勢いにまかせて「臨床研究デザイン塾」に参加いたしました。
参加して本当によかった!
勉強になった!
人生変わった!
と心底思っております。https://t.co/bv4H1MZ5wV
ちょうど野戦病院で手術の修練に明け暮れていたころでしたので、本当に勉強になって、人生の心構えが変わりました。
第2回だったので、2014年のころだったでしょうか。
時が経つのは早いですね。
福原俊一先生の講義を聞いて、鳥肌がたったのを覚えています。
臨床医が論文を書くことの意義
それで、臨床医が論文を書くことの意義を
「臨床研究」
を通じて学んだんですね。
わたしの医師人生で、臨床研究を学ぶ機会が希薄だったことにまったく気づいていなかったわけです。
あのまま過ごしていたら視野がものすごく狭いままだったと思うと、とても恥ずかしいです。
わたしはこれまでずっと論文作成を軽視してきました。
— とぜんな脊椎外科医@四つ葉スパインクリニック (@yotsuba_spine) August 23, 2019
手術ができるのが優れた外科医だと。
わたしの友人は、優れた臨床医ばかり。
と同時に優れた論文筆頭者でもあります。
なぜ論文を書くのか?
論文になかったら、自分で論文化すれば、次の誰かの役に立つはず。https://t.co/yOoSMfdOAq
臨床医が論文を書く意義は
1. 科学的根拠に基づいた論理的施行のためのよい訓練になる.
2. 観察は緻密になり、治療への取り組みもより積極的になる.
3. 独善に陥らないための他流試合としての意義がある.
4. 自分の経験を客観的に後世に伝えることができる.
5. 世界の医療に貢献するという夢をもつことができる.
6. 医師に充実感と成長をもたらす.
とまとめてあり、とても感銘をうけております。
いい論文を書いている!を測るh-index
随分前置きが長くなってしまったのですが、今回紹介したいのは、h-indexという概念です。
これを紹介しているのは、活動を再開してくれた
「二択で迷ったらアグレッシブな方を選べ」
からです。
「研究者の戦闘力 ~h-index」
よろしければブラックホイスさんのツイッターもフォローお願いします。
手術で腰痛が治るって?https://t.co/7a0DltKF8I
— ブラックホイス (@c3go7bnlvTZxJxm) August 19, 2019
ブラックホイスさんの記事は以前
「BKPよ、おまえはすでに死んでいる!?」
でも紹介させていただきました。
論文の批判的読み方や、英語論文の書き方のひながたなど、とても勉強になるブログ活動を行ってくださっています。
ブラックホイスさんを語るに、避けて通れない臨床研究デザイン塾。
2014年に一緒に参加し、ブラックホイスさんはそのまま、福原俊一先生に弟子入りしていまいました。
ブログのタイトル通り、アグレッシブです!!
さて、いい論文を書いていることか?と言われても、どう評価していいのかはわかりません。
h-indexというのは、
端的にいうと、多くの人の参考になる論文、すなわち「よく引用される論文」になると思います。これは調べたらすぐわかるのですが、数が多すぎてこれをもとに「研究者の実力」を測るのは難しい。というわけで考案されたのがh-indexです。
h-indexは、「◯回以上引用された論文が◯本以上」という数値です。
h-index 5の場合は、5回以上引用された論文が5本以上あることになります。
なるほど、h-indexが高ければ、それだけ引用論文が多く、社会的にすぐれた論文を記載している参考値になるということですね!
この記事のオチは何かというと、私たちが敬愛する某Y先生はなんとh-index 32!いつ、どこでそんなに戦闘力高められたのでしょうか。関西弁さん、とぜんさん、今度からお会いするときは失礼のないようにいたしましょう。Y先生には是非日本の脊椎外科を牽引する1人になっていただきたいです。
ということで、ブラックホイスさん、ご丁寧に、わたしのh-indexも添付して、メールでお知らせしてくださいました(汗)
もちろん、ごめんなさい。としか言えない結果でした(笑)
本日のまとめ
まあ、大学の教授を目指しているわけではないと言ってしまえば、医療人としての発展はないと思います。
「私たちが敬愛する某Y先生はなんとh-index 32!」
うっひゃあ、すみませんって感じです。
それこそ手術の修練ばかりに視野が狭くなっていて、えらそうに手術の能書きをたれていた自分が情けないですね。
過去の自分をぶんなぐってやりたいです。
実は、某Y先生はわたしの初論文(邦文ですが)をイチから(ゼロから?)ご指導いただきました。
とても感謝しています。
結果的に、学会賞をいただくことになり、全部赤ペン添削してくださって、すでにわたしの書いた論文ではなくなっていたのですが、わたしの業績にしてくださいました。
今もほそぼそと論文書いてます!
ブラックホイスさん、関西弁さん、某Y大先生、ありがとうございます!




コメント
コメント一覧 (4)
いつも身につまされるブログ記事ありがとうございます。ブラックホイスさんにしか書けない内容で更新を楽しみにしております。
デザイン塾、もう幹部なんですね。同じ参加者だったころが懐かしいですね。
わたしは亀よりも遅いあゆみですが、成長を実感しています!
臨床研究の道標はバイブルですよね。ただ、当直業務がなくなってばっと読み通す力が低下してしまい、、、言い訳(T_T)
わたしもほそぼそがんばります!
まさに今デザイン塾真っ最中です。頑張ってこの世界に引き込みたいと思いますw